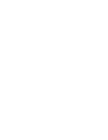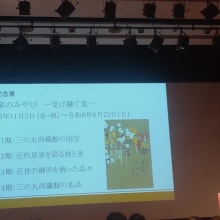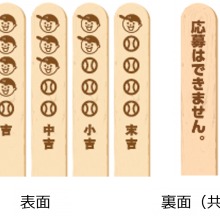その時、僕は、浜松町の職場で働いていた。入社してから続けている会計センターでの仕事に慣れ始めたころだった。定時で帰りたい日は、仕事中にさりげなく、「今日は定時で帰るんです」とアピールするなんていうこともやるようになっていた。すると、二、三期上の先輩社員たちが、みんな女性だったけど、「なに、なに、デート?」とうれしそうにしゃべりだした。定時を三十分くらい過ぎたころ、課長が「帰らなくていいのか」と声を掛けてくれた。
A子さんは、二つ年上だった。派遣会社から来た人で、僕の隣の席を使った。骨格がしっかりしていて大柄だったけど、座る時の姿勢が良くて、笑う時は、はにかみながらうつむいた。先輩たちは、「よかったわね」「仲良くするのよ」と楽しそうに声を掛けてくれた。でも、しばらくすると、残業中の会話にA子さんの話題があがらなくなった。
僕は、昼食は一人で取っていた。近くの食堂に入るか、お弁当を買って公園で食べるかのどちらかだった。
昼休みに公園に行くと、A子さんがベンチに座っていた。A子さんは顔を上げて辺りの様子を眺めていたので、すぐに僕に気がついた。近づくと、A子さんは、照れるよう下を向いた。
A子さんに声を掛けた。
「隣、いいですか?」
「はい」
「おひとりなんですか?」
「はい」
集団行動が苦手なA子さんは、先輩社員たちや派遣会社から来ているほかの人たちとは、いっしょに食事を取らないらしい。お昼の誘いを三日、断ったら、四日目からは誘われなくなったとのこと。
「せっかく、誘ってあげてるのに、こないのよ」
そう陰口を言われ、「一人でお昼を食べるのはかわいそうな人」と考える女の人たちから、完全に浮いてしまっているそうだ。
飲みに誘ったら、了解してくれた。
金曜日の夜に、会社の外で待ち合わせをして、有楽町や新橋の居酒屋を回った。たくさん、会話をした。A子さんが長崎から出てきたこと、地元の信用金庫で働いていたこと、故郷の彼氏が帰りを待っていること。
A子さんは、三か月で職場を辞めてしまった。アパートを引き払って、実家に帰るそうだ。
最後の夜に、二人で東京タワーに登った。夜の東京は晴れていた。
A子さんにお礼を告げた。
「いろいろと、ありがとうございました」
「こちらこそ」
「君のこと、ちょっと、好きだった」
「わかってました」
「何もしないから、目をつぶって」
十五分くらい、キスをした。
(竹内みちまろ)